「家賃と同じ金額で住宅ローンを」と不動産屋に言われたら注意したい3つのこと
賃貸と住宅購入、どっちが良い?
今賃貸に住んでいる方は毎月家賃を払い続けており、この支払いをローンの支払いにして家を買った方が良いのでは、と悩んでいる方も多い事でしょう。
国土交通省の平成30年住生活総合調査報告書によれば、以下のように日本の持ち家率は高くなっています。
| <持家と借家> | |
|---|---|
| 住宅のタイプ | 比率 |
| 持家 | 70% |
| 借家 | 30% |
借家に住む30%のうち、住み替えの意向を持つ人の中で、特に夫婦または子供をもつ家族では借家から持家へ今後5年以内に住み替え意向を持つ割合が多くなっています。
| <家族構成別今後5年以内の住み替え意向> | ||
|---|---|---|
| 借家→持家 | 借家→借家 | |
| 単身64歳以下 | 24.1% | 58.5% |
| 夫婦64歳以下 | 48.6% | 31.5% |
| 親と子 | 44.7% | 24.6% |
| 単身65歳以上 | 19.6% | 42.3% |
| 夫婦65歳以上 | 12.3% | 20.1% |
一方、持家に住む人の不満率は19.9%、借家に住む人の不満率は25.3%と多少借家の方の方が不満率は高いものの、74.7%が満足しています。
家を購入する場合は家が一生で大きな買い物となり、多くの人は住宅ローンにより人生最大の借入金を負い、その分支払いも大変です。
借家にも借家のメリットがあることから、このまま賃貸に住み続けるのか、住宅を購入するのかは慎重に考える必要があります。そこで、賃貸、購入のそれぞれのメリット・デメリットを知り、自分に適した選択をしていくのがいいでしょう。
(参考)国土交通省 平成30年住生活総合調査報告書
001358279.pdf (mlit.go.jp)
賃貸に住み続けるメリット・デメリット
メリット
駅に近いところでマンションまたは土地を購入しようとすると、その購入資金は多額になるため、その結果駅から遠いところを購入せざるをえません。賃貸なら立地と家賃は比例するものの、基本的には立地の良いところにあることが多く、駅に近い便利な場所に住むことができます。
そして、家を購入してしまうとかかる固定資産税、マンションなら修繕積立金、老後にはリフォーム費用などが発生し、大きなローンの返済に縛られます。
賃貸は、経年劣化してもまた新しいところに住み替えすればよく、生活環境に合わせて臨機応変に住み替えすることができます。ローンは必ず返済しなければなりませんが、賃貸であれば収入がへったときは家賃が安いところに住み替えができます。
デメリット
借りものなので、基本的に穴をあけることができず、自分好みにすることができません。すでに建てられている物件ということもあり、注文住宅のように、自分の好みの間取りにすることもできません。
老後長生きしたときには、常に毎月家賃がかかるため、それを不安に感じる人も多いです。
次に、住宅を購入したときのメリット・デメリットを紹介します。
住宅購入をするメリット・デメリット
メリット
一軒家なら騒音を気にしなくて済み、庭、ペットを飼えるなど子どもが育てやすい、または自分が過ごしやすい環境にすることができます。
家を子どもに残すこともでき、売却することもできます。毎月のローンの返済はありますが、何も残らない賃貸と異なり最終的には資産となります。
住宅ローンには団体信用保険の加入が義務付けられており、返済中に返済者に万が一のことがあればローンの返済はなくなり住宅を残された家族に残すことができます。
また、最近では団体信用保険に死亡時または高度障害時の保障だけでなく、三大疾病や入院が長期に及び働けないときなどの手厚い保障を付加することが可能となっています。
安定的な生活を送ることのできる住宅を購入するための住宅ローンは政府の施策が手厚く、住宅ローンは非常に低金利となっており、住宅ローン減税としてローン残高の0.7%を最大13年間減税するする制度もあり、支払利息の負担が少なくなっています。
デメリット
デメリットはローンによる返済の負担が挙げられます。
返済があるため、仕事を気軽に変えること、やめることができなくなります。また、住宅を購入することで保有中にかかるコストがあります。不動産取得税、固定資産税、修繕費等が挙げられます。
「家賃と同じ金額で住宅ローンを」と不動産屋に言われたら

2012年を境に住宅価格が上がり、特に首都圏のマンションはその傾向が顕著です。
そのため、昔に比べるとどうしても購入価額は大きくなりがちです。
それでも、マイナス金利下の低金利で変動金利の適用金利は0.5%を下回る水準で借りることができるので、借入金額の割には支払利息を含めた総返済額は少なく済みます。
不動産屋さんに「家賃と同じ金額で住宅ローンを組めますよ」と言われても、確かに毎月の返済額は今支払っている家賃と同じぐらいかもしれませんが、借入金額に対して毎月の返済額を家賃並みに抑えようと考えると、どうしても30~35年の長期の返済になると考えられます。
今の年齢から30~35年のローンを返済すると何歳になるか考えると、40歳で借りると75歳まで、35歳で借りても70歳までローンが残ります。
昔は年功序列の時代であり定年で退職すれ大きな退職金を受取れたため、それで返済するという手もありましたが、将来は退職金が少ないまたはないかもしれません。または、転職する可能性も否定できません。
そのため、退職金をあてにせず返済できるかどうかを確認し、無理のない借入金を決めて、その金額の範囲内で家を決めるべきでしょう。
住宅ローンは収入が安定的にあれば借りることができますが、無理のない借入れかどうかまで銀行は見てくれません。またいくら収入があっても、その収入をどのように使うかは人によって異なります。
そして、リフォーム費用の相場は100~1,000万円、老後の毎月の取崩し総額は700~1,000万円、さらに介護費用の平均572万円(一時費用平均74万円、月平均8.3万円、介護期間平均約5年)を考慮すると1,300~2,500万円は老後のために準備しておく必要があります。
以上より、家を見る前に借入金の金額を以下のステップで決めましょう。
借入金の金額の決め方
まず、老後までのライフプランを立てましょう。
子どもの教育費にどれだけかけるか貯めておきたいか、老後資金はきちんと残るか、ライフプランシミュレーションをすることでしっかり確認します。
シミュレーションは自分でエクセル作成、インターネットでのシミュレーション、FPに相談するなどして作成することができます。
現在住宅ローン利用者の70%超が変動金利を選択しています。
現在変動金利は0.2~0.6%と非常に低金利で借りることができますが、変動金利は適用金利が6ヵ月ごとに変動する可能性のあるものです。
今は適用金利が低くても将来金利が上がった時に総返済額や毎月の返済額が増える可能性があります。毎月の返済額が多少増えても無理のない毎月の返済額になるような借入金額と返済期間にしましょう。
また、返済はボーナス払いの割合が大きくならないようにするべきです。
ボーナスは会社の業績が良いときのみにでるものです。最悪ゼロとなる可能性もあるため、できるだけボーナス払いの金額は少なくしておくのがおすすめです。
借入金額の目安を決める前に家や土地を見てしまうと、どうしても高い方が魅力的に見え、借入金額が大きくなってしまう可能性があります。まず、借入金額を決めてから家を見るようにしましょう。
住宅費用以外の「諸費用」にはどんなものがある?
住宅を購入すると、ローン以外に以下の費用もかかります。
住宅を購入した場合にかかる費用
まず、住宅を購入すると不動産取得税がかかります。
これは取得時に1回のみ支払い、売買取得時は登記後4か月程度後、建築の場合は取得後6~1年後に納税通知書が郵送され、納付が必要になります。目安は10~20万円程度で、住宅の取得の場合軽減措置もあります。
そして、不動産を保有していると、保有しているだけで税金がかかります。
これを固定資産税といいます。保有していない限りかからないため、賃貸ではかからない費用です。
固定資産税は、1月1日時点で土地・建物の所有者に対してかかります。一定の要件を満たす住宅を購入したときは、5年または7年間固定資産税が軽減されます。
建物や土地の種類や場所によって異なりますが、建物と土地合わせて年間15~40万円かかります。これを4月に一括で支払うまたは4月7月12月3月に4回の分割で支払います。
住宅を取得してからしばらく経つと経年劣化します。そのため、住宅のメンテナンス費用が必要になってきます。一戸建ての場合、屋根や外壁、キッチン、お風呂等の修繕またはリフォームで平均556万円かかっています。
マンションの場合、共用部分の修繕費は次の解説する修繕積立金で賄われます。
マンション買うなら必ずチェック!修繕積立費と管理費
マンションのランニングコスト
マンションは、購入した後も毎月継続的に費用がかかり、ローン完済後にもその支払いは続きます。マンションには、主に管理費と修繕積立金、車を保有する方は駐車場代が別途かかります。特に、修繕積立金は年数の経過により金額が大きくなることがあるため、注意が必要です。
管理費
共有部分の清掃費用、管理人への報酬費用、共用部分の電気代や水道料金等の光熱費、保守点検費用等。管理費用は15,000~20,000円程度、タワーマンションの場合は20,000円以上することがあります。基本的に値上げはないですが、管理にかかるコストの増加、管理会社を変更したときに、値上がりすることがあります。
修繕積立金
管理費は建物を管理する費用であるのに対して、修繕積立金は建物の経年劣化から建物を維持するための費用です。
建物の経年劣化により劣化した建物は、外壁の補修など定期的な維持修繕が必要です。
外壁の補修のような維持修繕費は毎年行う必要はありませんが、行われるときは多額の費用が必要になるため、その費用を拠出するために毎月修繕積立金として所有者から徴収し、積み立てておきます。
そして、その積み立てられた資金は、修繕計画の通り定期的な修繕のときや自然災害等により毀損した部分の修繕するときに使われます。
修繕積立金はどのぐらいかかる?
修繕積立金の金額は、以下が目安となります。
修繕積立金(目安)=以下の表の目安金額×専有床面積
| <専有床面積当たりの修繕積立金の額> | ||
|---|---|---|
| 建物の階数 | 建築床面積 | 平均値 |
| 15階未満 | 5,000㎡未満 | 218円/㎡・月 |
| 5,000㎡~10,000㎡ | 202円/㎡・月 | |
| 10,000㎡以上 | 178円/㎡・月 | |
| 20階以上 | 206円/㎡・月 | |
※20階以上は修繕に特別な足場が必要となるため修繕費は高くなる。また、15階以上20回未満は、15階未満と20階以上の間の金額に収まると考えられます。また、機械式駐車場の場合さらに+α(7,085~14,165円/月)かかります。
例えば、専有床床面積75㎡、マンションの建物が15階未満、5,000㎡未満だった場合、修繕積立金の目安は、218円×75㎡=16,350円/月となります。
毎月、管理費15,000~20,000円、修繕積立金16,350円の計30,000~40,000円程度かかると考えておいた方が良いでしょう。
ただ、修繕積立金は建物に必要な修繕を行うものであり、一戸建てでも当然修繕費はかかります。一戸建ての修繕費は自分で貯めた資金または借入れにより一括で支払いますが、マンションの修繕積立金はそれを毎月少しずつ積み立てていると考えることもできます。
年数がたつと修繕積立費が大きく値上げすることも
修繕積立金は、将来必要な修繕費用の目標金額を計画し、その計画をもとに毎月徴収しますが、修繕積立金の支払い方法には、以下の2つの種類があります。

均等積立方式
築年数に関わらず毎月一定金額を積み立てる方式です。次の段階増額積立方式と比べると購入当初から少し高めの費用となりますが、年数がたっても一定金額の支払いで済みます。
段階増額積立方式
5年毎、10年毎のように段階的に金額が引上げされる方式です。購入当初は修繕積立金の金額が低いものの、年数が経つと大きく値上がりします。
新築マンションの場合、段階増額積立方式を採用している業者が多くなっています。
修繕積立金の積立計画表を購入前に確認し、値上がりした際に支払えるかどうか資金計画を立てるようにしましょう。その他、不足するときに一時金として一括で修繕積立金を徴収することもあります。
(参考)国土交通省 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」
修繕積立金及び長期修繕計画に関する (mlit.go.jp)
まとめ
住宅購入は賃貸に比べて様々なメリットもありますが、ローンを組むことにより返済に追われることになります。返済計画、ローン以外に住宅に係るランニングコストをよく確認したうえで、購入しましょう。
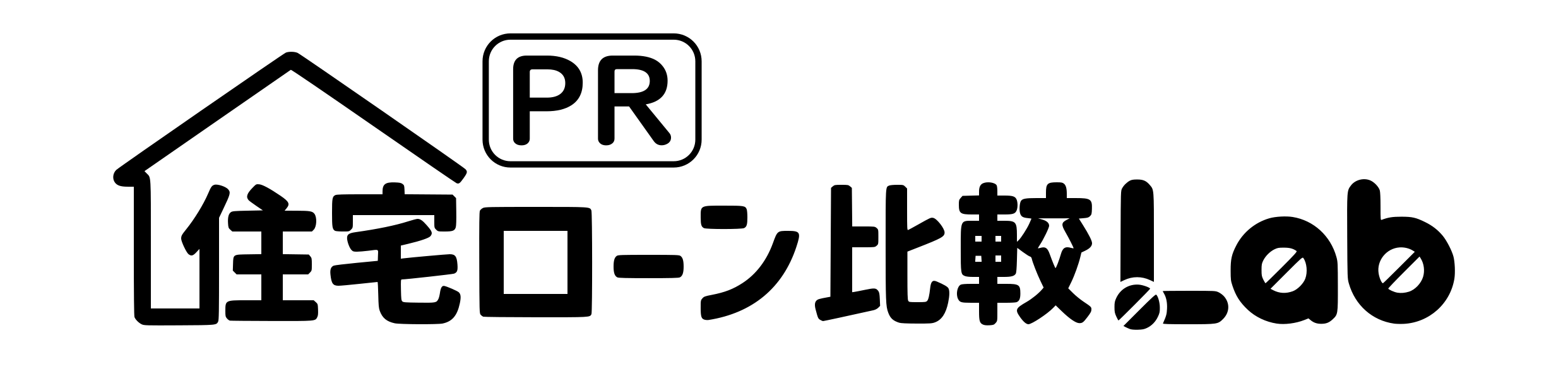 おすすめ低金利住宅ローン
おすすめ低金利住宅ローン